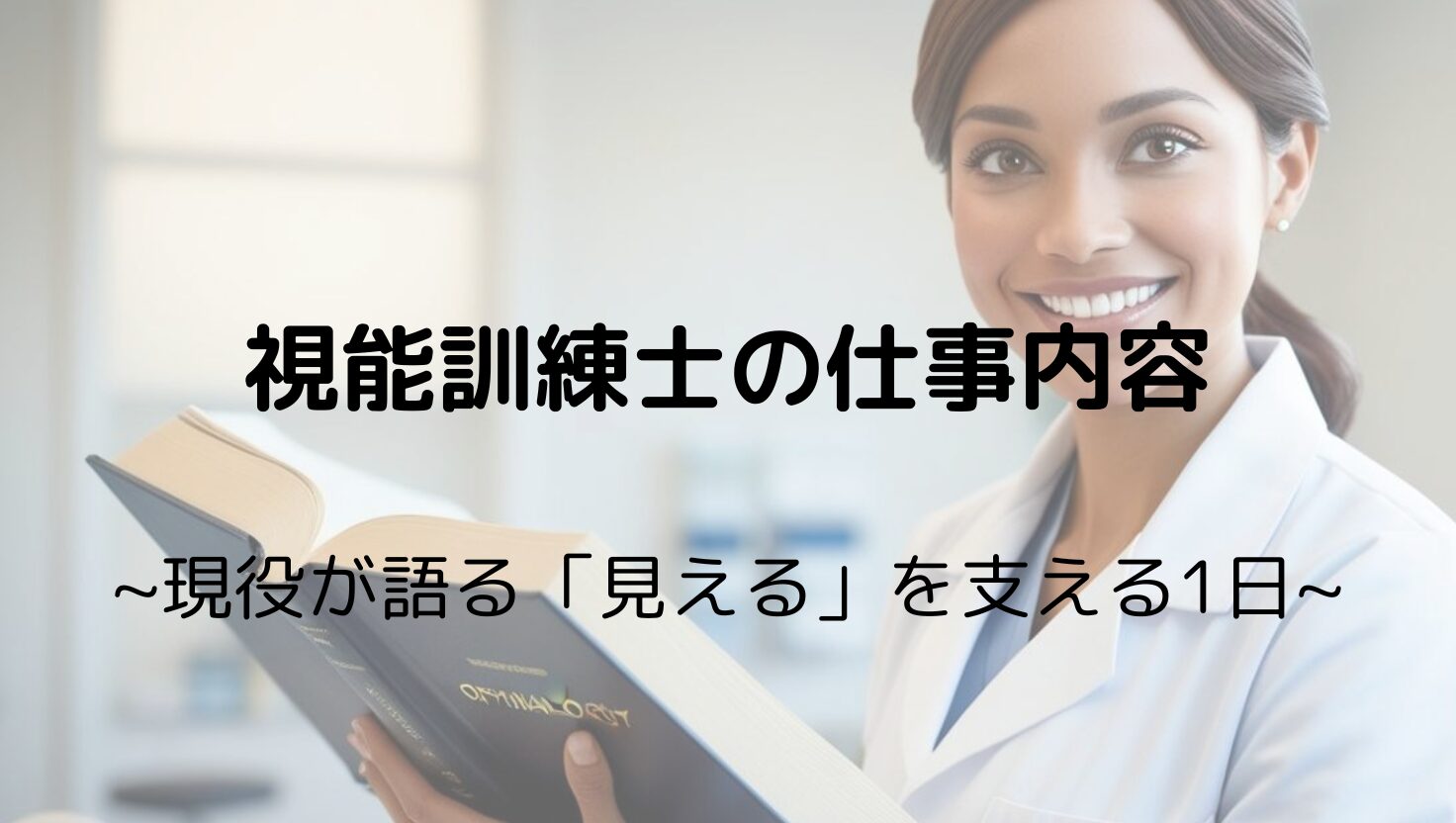視能訓練士の仕事内容、具体的にイメージできますか?もしくは、検査ばかりで単調な仕事だと思っていませんか?
この記事を読めば、視能訓練士のリアルな一日の流れ、検査の奥深さ、そして患者さんの笑顔に繋がるやりがいまで、すべてわかります。そのため漠然としたイメージが具体的なキャリア像へと変わるはずなのでぜひ最後までお付き合いください。

【ここでわかること】
・視能訓練士の仕事内容
・1日の流れ
・視能訓練士として仕事するために大切なこと

【自己紹介】
視能訓練士として約15年働いています。
あまり知られていない視能訓練士という職業についてブログで発信しています。
マニアックな仕事ですが、皆さん眼科で一度は出会ったことがあるはずなのでこれを機に覚えてもらえると嬉しいです。
視能訓練士ってどんな仕事?
「視能訓練士」という言葉を聞いて、どんな仕事を想像しますか?
「視力検査をする人?」と漠然としたイメージを持つ方もいるかもしれませんが、視能訓練士の仕事は、単に目の検査をするだけではありません。
患者さんの「見える」を支え、時には人生を左右するほど重要な役割を担う、専門性の高い仕事です。ここでは、その基本的な仕事内容から、医療現場での責任の重さまでを詳しく解説していきます。
主な仕事内容
視能訓練士は、国家資格を持つ視機能の専門家です。
眼科医の指示のもと、視機能に関するさまざまな検査や訓練、指導を行うことが主な仕事です。
- 視力検査
- 視野検査
- 眼底検査
- 手術前検査
- 小児の訓練
- ロービジョンの訓練 など
目の疾患は多岐にわたり、それぞれ専門的な検査や評価が必要不可欠です
視力検査一つとっても、単に数値を測るだけでなく、患者さんの年齢や状態に合わせた検査方法の選択、結果の正確な読み取りが求められます。このように、視能訓練士が行う検査は、医師が正確な診断を下し、適切な治療方針を決定する上で非常に重要な根拠となります。
診断を左右する責任の重さのある仕事
視能訓練士の仕事は、患者さんの視機能に影響を与える責任を伴います。
私たちが提供する検査結果の正確性が、医師の診断やその後の治療効果を大きく左右します。緑内障の視野検査でわずかな異常を見落とせば、病気の早期発見が遅れ、患者さんの視機能に影響を及ぼす可能性があります。また、小児の弱視訓練では、早期に適切な訓練を始めなければ、将来の視力発達に大きく影響することもあります。このように、視能訓練士は単なる「作業者」ではなく、高度な知識と技術、そして細心の注意が常に求められる、責任ある立場だと言えます。
全ての年代の「見える」を支える仕事
視能訓練士は、あらゆる年齢層の患者さんの視機能を支えています。
赤ちゃんの斜視や弱視から、学童期の近視、成人期の眼疾患、そして高齢者の白内障や緑内障など、目の問題は年齢を問わず発生します。小さな子どもには遊びを取り入れた検査で集中力を引き出し、高齢者には理解しやすい言葉で丁寧に説明するなど、それぞれの年代や病状に合わせた柔軟な対応力が求められます。このように、多岐にわたる患者さんと日々向き合う中で、彼らの「見える」をサポートし、生活の質の向上に貢献できる仕事です。
【リアルな一日密着】視能訓練士である私の一日
視能訓練士の仕事は、患者さんの「見える」を支える非常にやりがいのある専門職です。そんな中で「実際にどんな一日を送っているんだろう?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここでは、眼科クリニックに勤務する私自身の一日を追いながら、リアルな仕事の風景を具体的にお伝えします。
午前:午前診察のスタート!検査ラッシュ
一日の始まりは、クリニックの開院準備から。午前中は、特に多くの患者さんが来院するため、検査ラッシュとなることがほとんどです。
8:15 勤務開始、機器の準備
8:30 午前受付開始、検査スタート(約120人ほど)
視力検査・視野検査・眼底検査を当番制で役割を決め、各自検査に取り組む
途中、午前の手術の立ち合いが数件あり
12:00 検査が落ち着く
出勤後、まず使用する検査機器の電源を入れ、正常に作動するかを確認します。眼圧計や視野計、オートレフケラトメーターなど、多数の機器を扱うため、日々の点検は欠かせません。
その後、診察開始と同時に次々と患者さんが来院し、午前中は休む間もなく検査業務に集中します。
午前中は一般的な外来患者さんの来院が多いので、基本的には視力検査、視野検査、眼底検査をおこないます。

午前中の検査ラッシュが終わると、ようやく一息つける昼休憩。午前中の検査を振り返りながら、午後の業務に備えます。
午後:専門外来と訓練指導、患者さんと向き合う時間
午後の診察は、午前中とは少し趣が変わり、より専門的な検査や、患者さん一人ひとりに深く向き合う視機能訓練の指導が中心となります。患者さんの「見える」を具体的にサポートする、視能訓練士の腕の見せ所とも言える時間です。
13:30 午後の受付開始、専門外来スタート(約70人ほど)
*曜日によって、小児眼科・ロービジョン外来・緑内障外来・網膜外来などわかれています。
*各特殊外来に必要な検査や訓練をおこなう時間です。
*途中、午後の手術の立ち合いあり
17:30 受付終了、片付け、退勤
午後は緑内障や網膜疾患、小児眼科やロービジョンなど、特定の目の病気に特化した専門性の高い検査が多くなります。これらの検査は、医師が正確な診断を下し、治療方針を決定する上で極めて重要な情報源となるため、常に高い集中力と正確性が求められます。
斜視弱視訓練
特に視能訓練士の腕の見せ所として、子どもの弱視や斜視に対する視機能訓練の指導があります。これらの視機能の問題は、早期に適切な訓練を行うことで視力の発達を促し、将来の「見える」を大きく改善できる可能性があります。
弱視の子どもにアイパッチ訓練の目的を分かりやすく説明したり、斜視の子どもには自宅でできる眼球運動のゲームを教えたりします。子どもたちが飽きずに訓練を続けられるよう、遊びの要素を取り入れたり、親御さんとの連携を密にしたりと、様々な工夫を凝らします。

訓練の成果が出て、子どもの視力が向上した時の喜びは、この仕事の大きなやりがいの一つです。
ロービジョンケア
視能訓練士はロービジョンという、病気や事故などで視力回復が難しい方々の生活の質を向上させるための支援も行います。
残された視力を最大限に活用し、日常生活の困難を軽減することが、彼らの自立や社会参加に繋がるように、拡大読書器や遮光眼鏡など、患者さんの状態に合わせた補助具の選定や使い方を指導します。
また、家の中での動線や照明のアドバイス、点字ブロックの活用法など、日常生活で役立つ具体的な情報も提供します。

患者さんが「これならできる!」と希望を見出す瞬間に立ち会えることは、視能訓練士にとって大きな喜びであり、この仕事の社会貢献性を実感できる瞬間です。
視能訓練士の仕事で「大変!」「面白い!」ことは?
どんな仕事にも、大変なこととやりがいがあり、視能訓練士の仕事も例外ではありません。
「検査ばかりで単調なのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実は奥深く、そして人間味あふれる仕事です。ここでは、現役の視能訓練士が感じる「大変」と感じる瞬間と、「この仕事を選んでよかった!」と心から思えるやりがいについて、本音で語ります。
大変なこと①常に知識と技術を磨き続ける
視能訓練士の仕事は、常に新しい知識や技術を学び続ける努力が不可欠であり、これが大変だと感じる側面の一つです。眼科医療は日進月歩で進化しており、新しい疾患の発見、治療法の開発、そして何よりも最新の医療機器が次々と導入されます。
学会や研修会に定期的に参加し、最新の検査機器の操作方法を習得したり、新しい眼疾患に関する知識をアップデートしたりしています。これは、日々の業務に加え、自身の時間を割いて行う必要があり、正直なところ楽ではありません。しかし、患者さんに最善のケアを提供するためには、生涯にわたる学習が必須であり、これがプロとしての責任だと感じています。
大変なこと②患者さんの「見える」を左右するプレッシャー
視能訓練士の仕事は、患者さんの「見える」という大切な機能に直結するため、常に大きなプレッシャーと隣り合わせです。
私たちが実施する検査結果は、医師の診断や治療方針に直接影響を与えます。視野検査で緑内障のわずかな進行を見落としてしまえば、患者さんの視機能が失われるリスクを高めてしまう可能性があります。また、特に子どもの弱視訓練では、訓練の成果が将来の視力に大きく関わるため、結果が出なければという焦りや責任を感じることもあります。このように、一つ一つの検査や訓練に細心の注意を払い、正確性を追求する精神的な負担は、この仕事の「大変」な部分と言えるでしょう。
面白さ:「ありがとう」が原動力!患者さんの笑顔に触れる喜び
視能訓練士の仕事は大変なことも多いですが、それ以上に患者さんの「見える」を取り戻す手助けができ、「ありがとう」と感謝される瞬間に大きなやりがいを感じます。
自分たちの専門的な知識と技術が、直接的に患者さんの生活の質の向上に貢献できます。長い訓練を経て視力が向上した子どもの「見えるようになった!」という満面の笑顔や、新しい補助具を使って外出できるようになった高齢の方の「ありがとう、これでまた旅行に行けるよ」といった言葉を聞くたびに、この仕事を選んで本当に良かったと心から思います。このように、人の役に立ち、感謝される喜びは、日々の努力を続けるための何よりの原動力となっています。
視能訓練士として仕事をするために大切なこと
視能訓練士は、国家資格を持つ専門職であり、一度資格を取れば終わりというわけではありません。
医療の進歩は速く、患者さんのニーズも多様化しているため、常に自分自身をアップデートしていく必要があります。ここでは、視能訓練士として長く活躍し、さらなる高みを目指すために、日々の業務の中で大切にすべきことについて深掘りします。
医療の進歩についていく「生涯学習」の姿勢
視能訓練士として成長し続けるためには、「生涯学習」の姿勢が何よりも大切です。
自ら学び続ける意欲がなければ、時代の変化に取り残され、患者さんに最善の医療を提供することはできません。常にアンテナを張り、知的好奇心を持って学び続けることが、視能訓練士としての質を高める上で不可欠です。
患者さんと心を通わせる「コミュニケーション能力」
視能訓練士には、患者さんと心を通わせる高いコミュニケーション能力が求められます。
目の検査や訓練は、患者さんの協力なしには成り立たちません。緊張している子どもには優しく話しかけて不安を取り除いたり、高齢の患者さんにはゆっくりと分かりやすい言葉で説明したりと、相手の状況に合わせた話し方を心がけています。単に指示を出すだけでなく、相手に寄り添い、信頼関係を築くことで、より正確な検査結果に繋がり、患者さん自身の安心感にも繋がるのです。
小さな変化を見逃さない「観察力と注意力」
視能訓練士の仕事において、「観察力と注意力」は重要なスキルです。
なぜなら、患者さんの目の状態や、検査機器のわずかな異常、子どもの視機能訓練における微妙な変化を見逃さないことが、正確な診断や効果的な治療に直結するからです。
患者さんの目の動きや、検査データに表れるわずかな変動など常に注意深く観察しています。細部にまで意識を向け、異変を敏感に察知する力が、プロの視能訓練士として患者さんの安全と健康を守る上で欠かせない要素となります。
視能訓練士の仕事についてよくある質問
ここでは、視能訓練士の仕事を目指す方や興味がある方が抱きやすい疑問について、Q&A形式でお答えします。これまでの本文内容とは異なる視点や、補足的な情報を提供しますので、ぜひ参考にしてください。
Q1:視能訓練士の仕事は、男女比に偏りがありますか?
視能訓練士は、比較的女性が多い職種と言われています。しかし、近年では男性の視能訓練士も増えてきており、性別に関わらず活躍できる仕事です。
Q2:視能訓練士の働き方には、どのようなバリエーションがありますか?
視能訓練士の働き方は、眼科クリニックが最も一般的ですが、大学病院や総合病院、健診センター、リハビリテーションセンターなど多岐にわたります。それぞれの職場で役割や業務の専門性が異なり、例えば大学病院では研究や教育に携わる機会もあります。
Q3:視能訓練士として働く上で、体力的な負担は大きいですか?
視能訓練士の仕事は、基本的に立ち仕事が多く、検査機器の操作や患者さんの誘導などで体を動かす機会も少なくありません。しかし、過度な重労働が常に伴うわけではないので、一般的な医療職と同程度の体力があれば十分にこなせます。
Q4:患者さんとコミュニケーションを取るのが苦手でも大丈夫ですか?
視能訓練士の仕事では、患者さんとのコミュニケーションは非常に重要ですが、最初から得意である必要はありません。日々の業務を通じて、患者さんの話を傾聴する姿勢や、分かりやすく説明するスキルは自然と身についていきます。特に子どもや高齢者の方と接する機会が多いので、相手に寄り添い、信頼関係を築こうとする気持ちがあれば、コミュニケーション能力は必ず向上していくはずです。
Q5:視能訓練士として、英語などの語学力は役立ちますか?
近年、国際化が進む中で、外国人患者さんが来院する機会も増えています。必須ではありませんが、もし語学力があれば、自身の強みとして活かせる場面は確実に増えていくと考えられます。
まとめ
視能訓練士のリアルな仕事内容やその奥深さについて少しでも知ってもらえたのではないでしょうか。
眼科クリニックでの一日を通して、午前中の検査ラッシュや、午後の専門外来や視機能訓練指導における患者さんとの深い関わりなど、多岐にわたる業務内容をこなしています。
視能訓練士は、単に目の検査を行うだけでなく、眼科医の診断を左右するほどの正確な検査結果を提供する、責任ある専門職であり、常に時代ととも知識もアップデートしていく必要がある仕事です。
決して簡単な仕事ではありませんが、患者さんの「見える」を育み、感謝される瞬間に立ち会える喜びは、日々の努力を続ける何よりの原動力となり、社会貢献性の高い専門職として大きな達成感を得られる仕事ですよ。